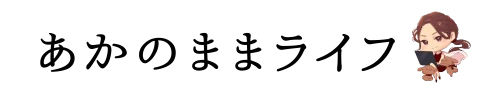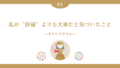今回は、娘と息子と一緒に参加したキッズマネースクールでの体験をまとめました。
親子で楽しく学びながら、お金との向き合い方について考えるきっかけになった一日。
学んだこと、気づいたことを、実践的なヒントも交えながらレポートしていきます。
キッズマネースクールとは?
キッズマネースクールは、子どもたちが「お金の大切さ」や「親への感謝」を学ぶ、体験型の金銭教育プログラムです。
「お金はありがとうと交換するもの」という考え方を、遊びを通して伝えています。
対象年齢は4歳~10歳ごろまで。
全国各地で開催されており、地域ごとのスクール情報も公開されています。
実はキッズマネースクールの存在は以前から知っていたのですが、
子どもの年齢や開催場所が合わず……。
そんな中、娘の小学校を通じて案内が届き、娘が「やってみたい!」と興味津々だったため、
4歳の息子も合わせて申し込みをしました。
当日は15名ほどの子どもたちが参加しました。
会場では、親と子が別々に座ることになっていて、はじめから離れて過ごす形に。
娘は心配していなかったのですが、息子がじっと座っていられるかどうかが少し不安でした。
ところが、意外にも静かに座って、先生のお話をしっかり聞いている様子にびっくり。
小さな成長を感じて、嬉しくなりました。
お金の大切さと親への感謝
講座では、
- 💰 お金の価値や使い方
- 🌍 世界のお金の紹介
- 🔄 物々交換から貨幣への流れ
といったテーマについて、子どもたちにもわかりやすく解説してくれました。
また、このあと行う「おみせやさんごっこ」に向けて、
- どんなお店なら商品が売れるのか
- どんな接客を心がければいいのか
を、良い例と悪い例を交えながら教えてくれたので、子ども達も楽しみながら参加していました。
例えば、
- 元気よく声をかけること
- おすすめをしっかり伝えること
- お客さんに笑顔で接すること
など、売れるためのポイントをわかりやすく説明してもらい、
子どもたちは、お客さんに喜んでもらう工夫や心構えを学びました。
娘も、自分で考えて手を挙げる場面がありました。
息子は、娘や周りの子たちに合わせて手を挙げていましたが、ピシッと手を挙げる姿が微笑ましかったです。
実際に先生に当てられたときは、何も喋れなかったようですが、それもいい経験ですね。
親向けの金銭教育
子どもたちが商品づくりをしている間、親たちは別室で金銭教育について聞きました。
ここでは、
- 💬 お小遣いの渡し方(定額制・お手伝い制)
- 📝 お小遣い契約書を作成する意義
- 📊 お金の使い方を計画させる重要性
など、実践的なヒントをもらえ、とても勉強になりました。
親向けに学んだ「おこづかい契約書」と「おこづかい計画」
特に印象的だったのは、
「おこづかい契約書を作り、親子で書面契約を交わす」という考え方です。
おこづかい契約書に書く内容の例
- 支給日:毎月◯日/毎週◯曜日 など具体的に決める
- 支給額:定額制か、お手伝い制か選ぶ
- お手伝い内容と金額設定
- おこづかいの使い道計画
おこづかい計画に含めるべき項目
- 💰 貯金するお金
- 🎁 ありがとうのお金(プレゼント・募金など)
- 🛍 自分で買うもののお金
※今回は触れられませんでしたが、本来は「投資するお金」という考え方も、将来的には重要になってきます。
こうして、自分でお金の使い道を考える習慣をつけることで、
金銭感覚を自然に育てていくことができるそうです。
おみせやさんごっこで「稼ぐ」体験と子どもたちの反応
後半は、子どもたちが「お店屋さんごっこ」に挑戦しました。
子どもたちはそれぞれ色塗りをした商品を準備し、
自分たちの手でお客さん(親たち)に接客しながら販売します。
親は、自分の子どもではなく、他のご家庭のお子さんのお店をまわって商品を購入。
子どもたちは、
「いらっしゃいませ!」
「おすすめはこちらです!」
「ありがとうございました!」
と、来てくれたお客さんに向けて、一生懸命対応をしていました。
「お金は自然には湧いてこない」
「働くことで初めて得られる」
そんな当たり前だけど大切な感覚を、遊びの中で自然と学んでいきます。
商品が売れるたびに娘はとても嬉しそうで、「全部売れた!」と誇らしげでした。
講座終了後に、先生から「おこづかい帳や契約書の紙を配ります」と聞き、娘は興味津々。
「自分で売ったお金をちゃんと数えたい!」と嬉しそうにしていました。
息子は最後の方は少し飽きた様子もありましたが、
それでも「売る」という体験を楽しもうとする姿が印象的でした。
二人とも、それぞれのペースで頑張りながら、
「お金は働いて得るもの」という感覚に少しだけ触れられた一日だったように感じます。
我が家の実践|おこづかい帳デビューと「ありがとうのお金」
講座終了後、配られたおこづかい帳の紙を手に取り、娘はワクワクした様子。
その後、私と一緒に相談しながら、書き込む準備を始めました。
おこづかいの振り分けも、娘自身が挑戦。
「貯金」
「ありがとうのお金」
「自分で使うお金」
というおこづかい計画の3つに沿って、
どんなふうに分けたらいいかを一緒に考えながらサポートしました。
我慢ばかりだと、お金を使う楽しさが学べません。
「たまには自分のために使っていいんだよ」と伝え、バランスを考えさせるようにしました。
「ありがとうのお金」って何?
娘にとって特に難しかったのが、「ありがとうのお金」のイメージ。
「ありがとうのお金ってなに?」と尋ねられたので、私はこう説明しました。
いつもお世話になっているおじいちゃんおばあちゃんに、ありがとうを伝えるためのお金だよ。
より具体的に伝えるために、
「おばあちゃん、どんな食べ物が好きだっけ?」と娘に質問。
すると、「おせんべい!」と即答。
「じゃあ、おせんべいを買えるくらいのお金を取っておこう」とアドバイスし、
「大体300円くらいかな?」と目安を伝えました。
娘は、目安の金額をもとに、自分が納得のいくように振り分けることができました。
お金を単に「使う」だけでなく、「誰かのために使う」「自分で管理する」感覚を、
少しずつ身につけはじめたように感じます。
まとめ|親子で楽しく「お金と向き合う」
今回のキッズマネースクール体験は、
子どもたちだけでなく、私自身にとっても大きな学びとなりました。
楽しみながらお金を学ぶこと、
自分で考え、計画を立てること――
これからも親子で、無理なく続けていきたいと思います。
私たちのように、何かきっかけがあると親子で“お金のこと”を話すチャンスになります。
機会があれば、ぜひお子さんと「おこづかい」について話してみるのも良いかもしれません。